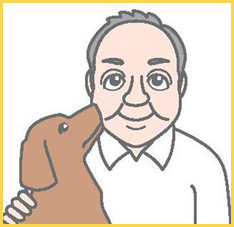無駄吠えの直し方
無駄吠えで困っている人はかなり多く、愛犬家向けのお悩み相談会を開催すると、相談内容のトップであったりします。
特に都会では、マンションなどで暮らしているワンちゃんも多く、いつも激しく吠えるために近隣の方からのクレームで真剣に悩んでいる飼い主さんがいます。犬側から見れば、無駄に吠えることはなく、必ず吠えなければならない理由があるのですが、その頻度が多すぎたり、寝ている夜中などに吠えられることでクレームの対象になるのです。正確には無駄吠えではなく、迷惑吠えだと言えます。犬種のせいや生まれつきの性格と諦めている飼い主さんもいますが、どんな犬でも無駄吠えは直すことができます。
吠える原因

愛犬の無駄吠えを直すには、まずは吠える原因を探る必要があります。一口に無駄吠えと言っても、威嚇して吠えているのか、怖くて吠えているのか、飼い主になにかを伝えようとしているのか、またはなにか要求しているのか、などに分けられます。一番多いのは、来客や通行人に対して吠えるケースで、その動機は警戒心や臆病が原因です。「こっちに来ないで!」と言っているのでしょう。
無駄吠えを直すためにNGな行動
愛犬の無駄吠えを直すのにしては良くないことが2つあります。
ひとつは吠えているのを止めさせるためにオヤツや大好きなオモチャをあげたりすること。もうひとつは、体罰や物を投げつけて驚かしたりすることです。吠えているのを止めさせようと魅力的な食べ物を与えるのは、反対に「吠えれば美味しいものがもらえる」と教えてしまうことになり、やがては来客や通行人もいないのに、オヤツを食べたくなれば吠えたりするようになりがちです。
次に体罰や驚かしてやめさせようとすることも良くない結果を生みます。怖くて吠えている子に、より怖い思いをさせるわけですから、仲にはパニックを起こす子もいます。仮に怖くて怖くて吠えるのが止まったとしても、同時に飼い主さんに対する安心感や信頼感は減っていきます。仮にうまくいって吠えるのをとめさせることが成功したとしても信頼感の欠如は他の問題の原因になったりします。
無駄吠えの直し方

愛犬の無駄吠えを直すには、吠えたら叱られることを教えると同時に、吠えなければ褒められることも教えなければなりません。叱るだけでは、自分から吠えないようにしようと思う犬には育ちません。
具体的な教え方
1、友人に頼み数分おきにドアチャイムを鳴らしてもらったりします。飼い主さんは愛犬にリードをつけ、玄関で待ちます。チャイムが鳴り、愛犬が吠えたら、すかさず口を下顎から押さえ、目を見てしっかり叱ります。その後、吠えるのを止めたままで一転して優しく褒めます。
2、そして、最初と同じ位置にたち、数分後のチャイムを待ちます。次のチャイムが鳴ったら、前と同じように口を押さえ、目をしっかり睨んで叱り、吠えるのを止めさせてから優しく褒めます。
3、数回 同じ事を繰り返します。やがて何回目かの時に、愛犬がこれまでと違う声を出します。チャイムが鳴った時に、それまでは「ワンワン」と吠えていた子が「グフグフ」などとの声に変わります。これは愛犬が迷い始めている証拠なので、この時には叱らずにすかさず笑顔で褒めます。
4、これも数回、繰り返します。やがて、「グフグフ」もなくなり、チャイムが鳴ると、吠えずに横の飼い主さんの顔を見上げるようになります。その顔が見えたら優しく褒めてあげてください。
吠えたら叱られるが、吠えなければ褒められると教えていくのです。無駄吠えでお困りの方は、是非、試してみてください。
犬の新着記事
-

犬が顔を舐めるのは愛情表現?意外な理由も紹介!
-

猫の片目異常に気づいたら知っておくべき症状と対策
-

飼い主の手を舐める愛犬の気持ちを理解しよう!実はこんな理由があった
-

犬が蕎麦を食べてもOK!与える量やおすすめの調理法を解説
-

犬に噛み癖をつけない、直すにはどうしたらいい?犬が飼い主を噛む原因と対処法
Ranking
-
 1
1
【獣医師執筆】犬が飼い主の手や顔を舐めるのはなぜ?愛犬の気持ちや、やめさせたい時の対処法など
-
 2
2
猫の片目異常に気づいたら知っておくべき症状と対策
-
 3
3
飼い主の手を舐める愛犬の気持ちを理解しよう!実はこんな理由があった
-
 4
4
【獣医師執筆】犬が一緒に寝たがるのはなぜ?犬と一緒に寝てもいい?獣医師が詳しく解説
-
 5
5
【獣医師執筆】犬に危険な植物・観葉植物は?室内や庭、お散歩時に要注意!
-
 6
6
犬が顔を舐めるのは愛情表現?意外な理由も紹介!
-
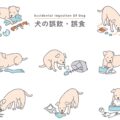 7
7
【獣医師執筆】犬が誤飲・誤食したかもしれない!チェックすべき症状と対処法。うんちで出るの?
-
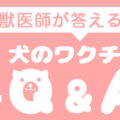 8
8
【獣医師が答える】犬のワクチンQ&A
-
 9
9
【獣医師執筆】犬の去勢手術はどうする?いつが適正?メリット・デメリットを知って考えよう
-
 10
10
【獣医師執筆】犬にネギは絶対あげちゃダメ。危険な量や症状、対処法を詳しく解説