
犬に噛み癖をつけない、直すにはどうしたらいい?犬が飼い主を噛む原因と対処法
子犬の甘噛み、成犬のお手入れ時の拒否噛みなどとに悩む飼い主さんは多いのではないでしょうか?
本記事では、犬の噛み癖の原因や対処方法、子犬のうちからするべき噛まないしつけ、成犬の噛み癖の直し方などについて、JKC東京東オール愛犬クラブ副代表、TOP DOGS開業25年以上、ハンドラー会社の代表も務める、吉田さんに詳しくお伺いしました。
ショーで活躍するワンちゃんのしつけや、噛み癖のあるワンちゃんのトリミングも多数対応してきた、吉田さんならではの役立つ知識満載です。
目 次
犬が飼い主を噛む原因

そもそも犬はなぜ噛むのでしょうか?代表的な原因を簡潔にまとめました。
口の中がむずがゆい
月齢によってはどうしても発生してしまうもので、乳歯が生え変わるタイミングに多いかと思います。「柔らかく口の中に入れてもいいもの」を代用として与えてあげましょう。口の中に異常がないか確認してあげるのも大切です。
しつけではなく、原因を突き止め解消してあげましょう。
遊びの一環
手を噛んではいけないことや力加減が分からず、興奮して強く噛んでしまうといったケースです。
本能的な欲求
犬種や血統によって度合いは異なりますが、犬が危険を感じた際や、大好きなおもちゃや食べ物を守る際など、野生的な本能が目覚めるスイッチはあります。歯を剥き出しにされ低い声で唸られるような状況です。
ストレスや恐怖
「水がとても怖い」「爪切りが嫌い」など、嫌いなことから逃れるために噛むこともあるでしょう。成犬の場合、これが一番多いのではないかと思います。
「噛んだら逃げられた!」という成功体験として覚えてしまっているケースや、「硬い毛玉を抑えられてブラッシングされ、痛かった」などの、過去のトラウマから噛んでしまうといった、多くの理由があると思います。
防衛反応
強く叩く、暴力を伴うしつけなど、生命への危機感や身体的な痛みを伴う行為への防衛反応で噛むこともあるでしょう。
犬の噛み癖予防、改善はどうしたらいい?

【1】噛まれてしまった時の対処法
甘噛みや本気噛みなどで手を噛まれてしまった場合

声を出さず
手を動かさず
できるだけ低い声で端的に「いけない、NO(ノー)」と注意する
大事なのは、ダメな行為であることが伝わるように、声色を変えて注意することです。
手を引っ込めたり騒いだりすると、子犬は「遊び」と勘違いし、むしろ噛み癖が強くなる場合がありますし、「手を噛んではいけない」ということを学ばず、大きな怪我につながる危険性があります。
また、飼い主さんより優位であると思わせてしまうと、言うことをきかない、攻撃性の高い性格になる危険性もあります。
力関係を明確にし、噛み癖を予防しましょう。
【2】愛犬を膝の上で優しくマッサージ

子犬の噛み癖予防にも、成犬の噛み癖対策にも有効なのが「膝上でのマッサージ」です。
子犬の場合特に、いきなり強く押さえつけてブラッシングするといった、怖がることをする前に、慣らすことからはじめましょう。こうすることで、不用意に口を開けない=噛まない犬になっていきます。
【心も体もほぐす!膝上マッサージのやり方】
膝上でなくとも、高さがあって、狭くて犬が自由に動きにくい場所であれば大丈夫です。地面に近すぎると、降りて逃げようと強く抵抗することがありますので、注意してください。
一番身近でやりやすいのは、椅子などに座って愛犬を膝に寝かせる方法かと思います。
①犬を膝上に乗せ、肩の付け根あたりを揉む
暴れてしまうこともあるかと思いますが、優しく抑えて揉みましょう。噛もうとしてきた場合は、口を軽く抑えて、イケナイと低い声で伝えましょう。
緊張や拒否反応で硬まった筋肉を根気よくマッサージでほぐし、まずはリラックスしてもらうことが大切です。
②落ち着いてきたら、マズルを優しく掴んで、顔をゆっくり上下左右に
③愛犬を仰向けにして、前面の肩の付け根あたりを揉む
仰向け時は特に暴れてしまうワンちゃんも多いと思いますが、そこでやめてしまってはダメです。優しく抑えてリラックスするまでマッサージをしましょう。
④落ち着いてきたら、仰向けのままマズルを優しく掴んで、顔をゆっくり上下左右に
仰向けでもだらんとリラックスし、身体を任せてくれるようになるまで、毎日少しずつ続けましょう。
これをすることで、身体を触られることへ恐怖心や抵抗感を緩和できますし、力では敵わないことを悟り、飼い主さんとの主従関係がはっきりするでしょう。そうすることで、お手入れなどの拒否噛みだけでなく、普段の噛み癖予防、対策につながります。
マッサージですので、愛犬とのスキンシップとして、ぜひやってみてください。
【3】実は一番大事!散歩の訓練!

一見噛み癖とは関係なさそうですが、一番大事なのは散歩の訓練です。
【1】【2】にも共通しているのは「力関係を明確にすること」。毎日行う散歩は、愛犬と飼い主さんの関係性が出やすく、ここを整えることが、あらゆる問題行動の改善に繋がっていきます。散歩時は、愛犬をきちんと飼い主さんの左に付けて歩くことが好ましいです。

首輪を用いて、散歩時の引っ張り癖を解消
普段はハーネスという方も多いかと思いますが、しつけの際は首輪を使用しましょう。
お散歩しつつ歩いて止まる、を繰り返してください。愛犬が飼い主さんの意向を無視して好きなところに行こうと引っ張ったら、ダメであることを伝えるために、首輪を飼い主さんの方向へ一瞬グッと強く引きましょう。
痛みを与えるのではなく、ショックを与えて「イケナイ!」と伝えることが目的ですので、執拗に何度も行う必要はありません。
ショックだけで言うことを聞いてくれない場合、初めはオヤツを活用してもいいでしょう。ただし、愛犬にあげるためにオヤツを下まで持っていくのはダメです。腰の少し上あたりなど、高い位置であげましょう。
おすすめはドッグランでの散歩訓練
散歩の訓練をしたいけれど、普段の散歩コースは自転車や車、人通りも多く難しい、声を出すのも恥ずかしい…という方も多いでしょう。そんな時にぴったりなのが、ドッグランです!
周囲の方の犬への理解が深く、安全であることはもちろん、周りに多くのわんちゃんや飼い主さんがいる誘惑の多い中で、しっかりしつけできることが最大のメリットです。
「愛犬の散歩をする」のではなく「飼い主さんの散歩に愛犬を同行させる」イメージで!
散歩に対する意識を変えることも大切です。
愛犬の運動や楽しませたくて散歩に行く、という方も多いと思います。もちろん重要なことですが、メインが「愛犬」になってはダメです。飼い主さんに寄り添って歩き、散歩コースも臭いを嗅ぐ場所も飼い主さん主導であることを意識しましょう。
そうすることで、急な飛び出しによる事故、禁止されている場所での粗相トラブル、他の犬や人へ噛みつき事故といったリスクを大幅に減らすこともできます。
子犬のしつけにはこれも有効!

クレートなどは、家族の目線に入らない場所において、要求吠えや甘えには応えない
子犬をお迎えしてすぐは、可愛くて可愛くて四六時中構ってしまい、少しでもキュンキュン言おうものなら、どうしたの?と様子を見に行ってしまうかと思います。これもやめましょう。
飼い主さんがいないとパニックになる、分離不安症になってしまったり、言うことを聞いてくれず、問題行動の原因になりかねません。
愛犬のタイミングではなく、飼い主さんのタイミングでお世話する、遊ぶということを、早い段階で徹底しましょう。
やりがち!NG対応

愛犬本位な、引っ張りあい遊び
運動不足解消やストレス発散に、おもちゃを噛ませて遊ばせるのは大丈夫です!
ただし注意して欲しいのは、飼い主さんが愛犬に負ける形で、おもちゃを引っ張り取られること。「自分の方が強い!」と思わせてしまうと、態度が変わってしまう可能性があります。
おもちゃは最終的に飼い主さんが取って終わる、もしくは、号令でおもちゃを口から離すように訓練しましょう。
おもちゃを取ろうとすると唸ってしまう場合は、遊びの時も首輪とリードを用いた訓練が有効です。おもちゃを離してくれない時は、リードを首より上に吊るように張り、「ちょうだい」などの号令をかけてください。号令だけで離してくれない場合は、少しだけ引っ張りましょう。
そしておもちゃを離してくれたら、すぐに飼い主さんの体の近くに隠す(飼い主さんの所有物であると伝える)、その上でまた遊ぶ、というように繰り返しましょう。
「おもちゃを離したら、また遊んでもらえる」と覚えさせることが大切です。
手を噛ませていないから大丈夫と思うかもしれませんが、愛犬が優位である状況が積み重なるとワガママになっていき、自分の要求が通らない=噛むということに繋がりかねません。
体罰を伴うしつけ
厳しさは大切ですが、強く叩く、言うことを聞くまで怒鳴りつける、などのしつけはダメです。痛みで支配するのではなく、根気よく教えていきましょう。焦りは禁物です。
自宅で無理やりするシャンプーやカット
自宅でのお手入れが全てダメというわけではありません。ただ、間違っていたり、あまりに無理やりなお手入れは、愛犬のトラウマとなり、噛み癖に繋がる危険があります。
「もつれにもつれて、硬くなった毛玉を無理やりブラシで引っ張る」「広い場所で、逃げる愛犬を強くおさえつけて洗う」など、痛みや恐怖につながるお手入れはやめましょう。
またトラウマを避けるためにも、お手入れはこまめにしてあげることが大切です。子犬を迎えたら、2日に1回はブラッシングをしましょう。ただし、痛がったらすぐにやめることも大切です。
「やり方が分からなくて不安」「お手入れ期間が空いてしまい毛玉などができた」などの際は、トリミングサロンをぜひ頼ってください。経験上、噛み癖に悩むワンちゃんの7割は、子犬の時にサロンでの施術を受けていない犬が多いです。お手入れのトラウマ防止や社会化の一環としても、役立つと思います。
まとめ

厳しい母犬や父犬になったつもりで、愛犬のための厳しさを
噛む行為は「自分が優位だと感じ、わがままになっている」「痛みや恐怖から逃げたい」が大きな原因かと思いますので、前者にはしつけと毅然とした対応を、後者には、体に触れられることに慣れてもらえるようマッサージをしたり、トラウマにならない対応をしてあげてください。
しつけはかわいそう…そう思う気持ちも分かります。ですが野生であれば、危険な行為をしたら、母犬が耳や鼻先、口先などに噛み付いて止めます。兄弟犬との遊びの中で、噛んだり噛まれたりと痛い思いをして、学んでいきます。
多くの子犬は、早い段階で母犬や兄弟と離されてしまいますので、そのような経験がないことが多いです。私も子犬を育てる際は、わざと母犬のふりをして噛んで教えることも多々あります。
可愛すぎて叱れないという気持ちはとても分かりますが、その子のための厳しさも愛情です。愛犬との日々を、より楽しく豊かにするために、意識を変えることからはじめましょう!
【関連記事】
犬にとってのトリミングとは?サロンと自宅の違い、料金や頻度の目安
TOPDOGS本店(東京都世田谷区深沢1-1-1)/TOPDOGS田園調布店(東京都世田谷区東玉川2-14-8)/来夢TOPDOGS 山梨店(山梨県山梨市下石森1000-3)
犬の新着記事
-

犬が顔を舐めるのは愛情表現?意外な理由も紹介!
-

猫の片目異常に気づいたら知っておくべき症状と対策
-

飼い主の手を舐める愛犬の気持ちを理解しよう!実はこんな理由があった
-

犬が蕎麦を食べてもOK!与える量やおすすめの調理法を解説
-

【獣医師監修】犬と猫のフィラリア、初期症状や予防法、薬の期間は?治るの?
Ranking
-
 1
1
猫の片目異常に気づいたら知っておくべき症状と対策
-
 2
2
飼い主の手を舐める愛犬の気持ちを理解しよう!実はこんな理由があった
-
 3
3
【獣医師執筆】犬が一緒に寝たがるのはなぜ?犬と一緒に寝てもいい?獣医師が詳しく解説
-
 4
4
【獣医師執筆】犬が飼い主の手や顔を舐めるのはなぜ?愛犬の気持ちや、やめさせたい時の対処法など
-
 5
5
【獣医師執筆】犬に危険な植物・観葉植物は?室内や庭、お散歩時に要注意!
-
 6
6
犬が顔を舐めるのは愛情表現?意外な理由も紹介!
-
 7
7
【獣医師執筆】犬にネギは絶対あげちゃダメ。危険な量や症状、対処法を詳しく解説
-
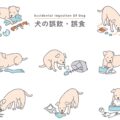 8
8
【獣医師執筆】犬が誤飲・誤食したかもしれない!チェックすべき症状と対処法。うんちで出るの?
-
 9
9
【獣医師執筆】犬の寒さ対策。愛犬は寒さが苦手?対策グッズも解説!
-
 10
10
【獣医師執筆】犬ににんにくはあげちゃダメ!症状や危険な量、対処法を詳しく解説





