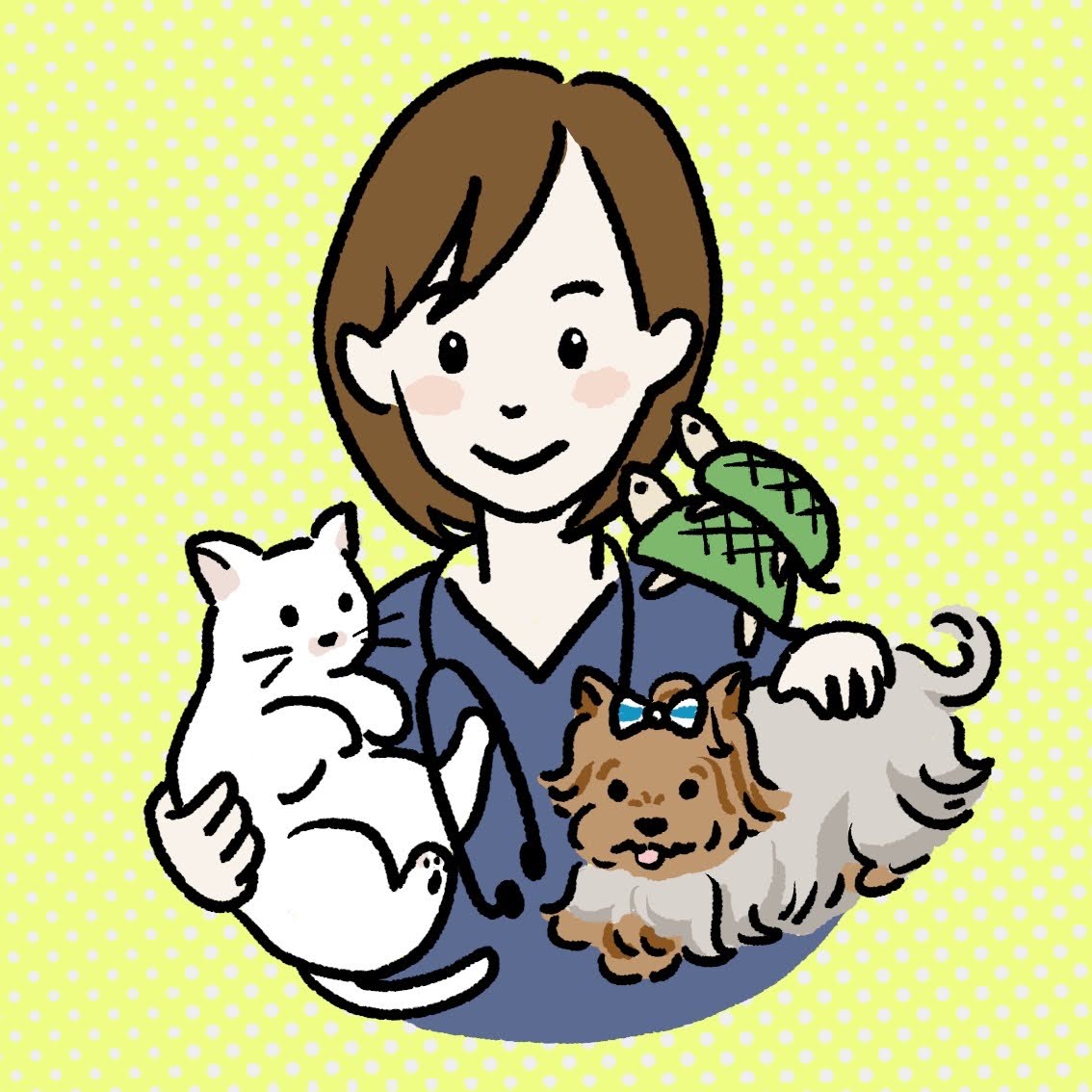【獣医師執筆】猫にネギ類は絶対NG。中毒をひきおこす量や症状、対処法を詳しく解説
ネギ類は、猫にネギ中毒(タマネギ中毒)を引き起こす危険な食材です。皮や葉、根などどの部位でも与えることはできず、少量でも危険です。加熱などの加工をしても危険性は変わりません。今回の記事では猫のネギ中毒の症状や原因、猫がネギ類を食べてしまった時の対処法などをお伝えします。
目 次
猫のネギ中毒の危険性

猫のネギ中毒の危険性と食べさせてはいけない食材や料理をお伝えします。
命の危険もある、溶血性貧血(ようけつせいひんけつ)
猫はネギ中毒になると「溶血性貧血(ようけつせいひんけつ)」をおこし、元気や食欲がなくなるなどの貧血症状が出ます。赤い尿や黄疸もネギ中毒で起こる症状のひとつです。ネギ中毒は悪化すると命の危険もあります。
どんな状態でもネギ類は危険!

ネギ類全般NG
食材として日本で日常的に食べるネギ類には、長ネギ、タマネギ、ワケギ、アサツキなどのいわゆるネギ類とニラ・ニンニク・ラッキョウがあります。これらはすべて猫にネギ中毒をひきおこす可能性があります。
外皮、葉、根っこなどの部位も同様に危険
食材の外皮、葉、根っこなどの部位も同様に与えることはできません。量に関してはあとで詳しく解説しますが、微量でも中毒の可能性があります。
生も加熱もNG
ネギ類は加熱しても危険性に変わりはありません。
微量でも危険性あり
猫のネギ中毒の原因として多いのは、食材そのものを生で食べるより、人間用に調理した料理を食べてしまうことです。特に猫の場合、ハンバーグやすき焼きなど肉類と一緒に調理されたネギを食べてしまうことがあり、微量でも危険です。
【猫のネギ中毒の原因として誤飲報告があった料理例】
- 味噌汁やスープ
- ハンバーグ
- 肉じゃが
- すき焼き
- 肉鍋
- 焼き鳥のネギマ
- おでん
- メンチカツ
- 牛丼、豚丼、親子丼などの丼もの
- チャーハン
野草や園芸にも注意
ネギ類は野山に自生していたり、園芸で植えられていることもあり、これらを食べて中毒を起こす可能性もあります。猫はもともと草を食べる習性があるため、野草や園芸のネギ類にも注意が必要です。
猫のネギ中毒の症状と致死量
猫のネギ中毒の症状と、どの程度の量を食べると危険なのかを解説します。
猫のネギ中毒の症状
猫はもともとよく吐く動物で、食欲にムラがある子も多いでしょう。体の不調を隠すのも上手なので、初期症状では気づかない場合もあります。ここでは猫のネギ中毒でみられる症状を、初期と重症化した場合に分けてお伝えします。
【初期症状】
- なんとなく元気がなくなる
- 食欲がなくなる
- 吐く
- 下痢
【重症化した時の症状】
- ふらつく・意識がもうろうとする
- 赤い尿・赤褐色の尿、あるいは緑黄色のような異常な色の尿
- 口の中やまぶたの粘膜が白っぽくなる
- 白目や口の中が黄色っぽく見える(黄疸になる)
- 口を開けて呼吸をする
これら以外でも、猫がネギ類を食べたあとに様子がおかしければネギ中毒を疑いましょう。
猫がネギ中毒をおこす量は?

1Kgの体重あたり5g以上(体重の0.5%以上)
ブラジルの論文では、猫では体重1Kgあたりわずか5gの摂取で中毒をおこすとされています。タマネギではほんのひとかけら程度、長ネギならほんのひと刻み程度でも危険だということです。
(参照)Allium species poisoning in dogs and cats
猫にネギ中毒の症状が出るまでの時間は?

翌日以降に出ることが多く、数日経過してから現れることも
猫はネギ類を食べるとすぐに吐くことがあります。これはネギ類によって気分が悪くなって吐いただけという可能性が高いです。本来の中毒症状は翌日以降に出ることが多く、数日経過してから現われる可能性もあります。
猫がネギ中毒かもしれない!とるべき対処法

猫がネギ類を食べてしまった時、飼い主様にできる応急処置は少ないです。すみやかに動物病院に相談しましょう。
・症状があれば1時間以内に受診を
何らかの症状が出ていれば1時間以内に受診するのが理想です。症状がでていなくても食べたことがわかっている場合はすぐに動物病院に相談しましょう。
・可能なら猫に水を飲ませる
動物病院に相談すると水を飲ませるように指示されるかもしれません。その場合は、常温の水をできるだけたくさん与えましょう。飲みたがらない場合や、意識のない場合は無理に与えずすぐに受診しましょう。
・食べたもの、時間、量をメモする
何をいつ、どの程度の量食べたのかをメモしておくと、受診の際に役立ちます。吐いたものや下痢をした場合、持参することを指示されることもあるので処理は獣医師に相談してからにするのが良いでしょう。
猫のネギ中毒、動物病院での治療
動物病院では口にしたものの量などが明らかな場合は、スピードを重視しすぐに治療に入ることもあります。また基本的には飼い主様からの聞き取り、血液検査などを行います。
●吐かせる
摂取後時間がたっておらず獣医師が吐かせられると判断した場合、「催吐剤(さいとざい)」という薬を用いて吐かせます。
●活性炭で吸着させる
活性炭を経口摂取させることで、中毒物質を吸着させる治療が行われることもあります。他の薬剤も吸着してしまう可能性があるため、他の治療との兼ね合いで使用を決定します。ネギ類を食べてからの時間が経過し過ぎていると効果がないこともあります。
●点滴などの投薬
点滴も比較的よく行われます。点滴によって循環を良くして、中毒物質の排泄を促す効果などがあります。赤血球の酸化を食い止めるため、抗酸化作用のあるビタミンCやビタミンEを点滴に混ぜることもあります。
●輸血
溶血性貧血が重度の場合は輸血を行うこともあります。
その他、胃洗浄を行ったりステロイド剤の投与を行うなど、猫の状態と獣医師の判断によって治療を進めます。
<関連記事>
ネギ類が猫に中毒をおこす理由

ネギ中毒の危険は比較的有名ですが、ネギ類の何が原因なのか、どのような流れで中毒が起こるのかまでは知られていないことも多いです。
原因物質は「有機チオ硫酸化合物」
猫のネギ中毒の原因物質はネギ類に含まれる「有機チオ硫酸化合物」です。
【中毒が起きるまで】
①猫がネギ類を食べると、有機チオ硫酸化合物が赤血球の「ヘモグロビン」を酸化させます。
②そして赤血球中のヘモグロビンが酸化すると、赤血球内に「ハインツ小体」と呼ばれる物質が出現します。
③ハインツ小体を持つ赤血球は、体内の「脾臓(ひぞう)」という臓器によって、老化した不要な赤血球だとみなされ壊されます。(この赤血球が破壊されることを「溶血(ようけつ)」と言います)
④溶血(赤血球が破壊されること)すると体では貧血がおこり「溶血性貧血」となります。
⑤その結果、元気食欲の低下や、ふらつきなどの症状が出るのです。
「有機チオ硫酸化合物」は熱にも加工にも強い
「有機チオ硫酸化合物」は熱にも強く、焼いたり煮込んだりした料理中のネギ類も危険性は変わりません。細かく刻んだり、他の食材と混ぜるなどの加工などでも危険性は変わりません。
猫は犬よりネギ中毒を起こしやすい
猫は犬と比較して、ネギ中毒を起こしやすいと言われています。その理由は、もともと持っているハインツ小体の割合が多いこと、猫の赤血球は酸化により、他の動物の2~3も多くのハインツ小体ができることが関わります。
(参照)Toxicology Brief: Allium species poisoning in dogs and cats
猫のネギ中毒に関してよくある質問Q&A
猫がネギ類をなめてしまっただけでも動物病院に行くべきでしょうか?
ほんのひとなめ程度であれば問題のないこともあります。数日間よく様子をみて、普段と様子が違ったらすぐに受診しましょう。舐めた量が不明な場合はすぐに動物病院に相談することをおすすめします。
猫がネギ中毒になった場合、どれくらいで治りますか?
初期症状の場合、適切な治療をすぐに受ければ数日から1週間以内に治る可能性が高いです。重症化した場合、入院なども必要となり治るまでの期間も長引く場合があります。
猫がネギの臭いを嗅いだだけでも危険ですか?
ネギの臭いを嗅いだだけで中毒症状をおこすことはありません。.ネギ類には強い臭いがありますが、もともと猫は生のネギ類の臭いを好みません。ただ臭いで猫の体調が悪くなることもありますので、近づけないようにしましょう。
ネギ中毒は猫など猫以外の動物でもおこりますか?
ネギ中毒の時の赤い尿は、赤血球が壊れてヘモグロビンが尿中に出る「ヘモグロビン尿」というものです。尿の酸性度によってヘモグロビンは赤や褐色になります。
猫のネギ中毒で、赤や赤褐色などの尿が出るのはなぜでしょう?
ネギ中毒の時の赤い尿は、赤血球が壊れてヘモグロビンが尿中に出る「ヘモグロビン尿」というものです。尿の酸性度によってヘモグロビンは赤や褐色になります。
猫がネギ類を口にしないよう徹底を!

ネギ中毒から猫を守るためには、ネギ類を食べさせないことが一番です。
猫は高いところや狭い隙間にも入れます。猫の手の届くところに食材を置かないように気を付けましょう。またネギ中毒の危険性をお子さんを含め家族全員で共有し、人のご飯は一切与えないなどルールを決めれば猫の健康を守ることにつながるでしょう。
施設を探す
猫の新着記事
-

長時間のふみふみ?猫の不思議な行動の秘密
-

猫が立てないときの対処法と予防策
-

猫がよろける原因とは?健康チェックのポイント!
-

猫の背中にフケが出る要因とは?理由と対策を徹底解説
-

【獣医師監修】犬と猫のフィラリア、初期症状や予防法、薬の期間は?治るの?
Ranking
-
 1
1
【獣医師執筆】猫が一緒に寝るのはなぜ?位置で気持ちは違う? 効果や注意点などを詳しく解説
-
 2
2
【獣医師執筆】猫の寒さ対策どうしたらいい?留守番、夜間の対策グッズや注意点などを詳しく解説
-
 3
3
【獣医師執筆】猫が異物を誤飲・誤食したかも!症状と対処法を知って命を守ろう
-
 4
4
【獣医師執筆】猫のダイエットどうしたらいい?そもそも肥満?運動、食事、期間など詳しく解説
-
 5
5
【獣医師執筆】猫の避妊手術はした方がいい?後悔しないために、時期や費用、リスクなどを知ろう
-
 6
6
【獣医師執筆】猫の顎ニキビ(猫ニキビ)はなぜできる?拭き方、 薬などのケア方法を詳しく解説
-
 7
7
【獣医師執筆】猫のフケの原因は病気?取り方や対処法、出やすい猫についても解説
-
 8
8
ここ最近急に猫が痩せたような気がします。どこか悪いのでしょうか。
-
 9
9
【獣医師執筆】猫が「ふみふみ」してくるのはなぜ?どんな気持ち?状況別に細かく解説
-
 10
10
【獣医師執筆】猫は生クリームを食べても大丈夫?適量とデメリットについて、与え過ぎ注意!