
皮膚トラブル(細菌性皮膚炎・アトピー性皮膚炎)と東洋医学【獣医師解説】
ペットの通院理由でも上位を占める皮膚トラブル、治療が長引くケースも多く、身体にかかる負担も気になります…。そんなとき、より自然に近い療法である東洋医学はどんなアプローチができるのでしょうか? 「いのちのために。」2回目は、皮膚トラブルと東洋医学について、モナ動物病院の関根 秀子先生にご執筆いただきました。
東洋医学でできること
西洋医学における皮膚病治療では、抗生物質やステロイドがよく処方されます。
そこに東洋医学的な治療や漢方を併用することによって、それらの薬を軽減したり中止することが期待できるでしょう。
次からは代表的な2つの皮膚病を紹介します。
細菌性皮膚炎と東洋医学

まずは細菌性皮膚炎です。細菌が皮膚に付着して炎症を起こします。
原因となる細菌を取り除く抗生物質を使えばよいのですが、東洋医学ではまず皮膚を整えることを考えていきます。
「湿熱熱毒」という炎症を起こし真っ赤になっている皮膚に「清熱解毒」という効果のある漢方薬を投与し、皮膚の熱を下げ毒を取ります。皮膚の状態を改善することによって本来の皮膚の持つ力を引き出し、自己治癒力を高めることで改善につなげるのです。
アトピー性皮膚炎と東洋医学
次にアトピー性皮膚炎です。アトピーは赤くなって痒い「湿熱」が特徴ですが、そこには皮膚以外の複雑な症状が関係しています。
たとえば、おなかの調子が悪いことは東洋医学では「湿」を発生すると考えます。また繊細な性格やイライラが皮膚のかゆみや熱を引き起こすと考えられています。
これらは皮膚とは関係ないように思われますが、おなかの調子を整えたり、精神面を整える漢方薬を処方することで症状の軽減につながります。

アトピーの犬です。アレルギー反応の出るものを食べたり、花粉の季節には皮膚が赤くなります。

漢方薬を服用し皮膚の発赤を抑えています。とても症状のひどいときやスギ花粉の時期などは抗アレルギー剤やステロイドなどを服用することもありますが、漢方を服用するようになってからは、以前にくらべて投与量は格段に減りました。
犬の新着記事
-

犬に噛み癖をつけない、直すにはどうしたらいい?犬が飼い主を噛む原因と対処法
-

【獣医師監修】犬と猫のフィラリア、初期症状や予防法、薬の期間は?治るの?
-

【獣医師執筆】犬の暑さ対策、エアコンなしはOK?快適に過ごすための工夫を詳しく解説
-

【獣医師執筆】犬猫のノミ・ダニ対策と見つけた際の対処法、予防などを詳しく解説。人間への影響は?
-

【獣医師執筆】犬の去勢手術はどうする?いつが適正?メリット・デメリットを知って考えよう
Ranking
-
 1
1
【獣医師執筆】犬が飼い主の手や顔を舐めるのはなぜ?愛犬の気持ちや、やめさせたい時の対処法など
-
 2
2
【獣医師執筆】犬が一緒に寝たがるのはなぜ?犬と一緒に寝てもいい?獣医師が詳しく解説
-
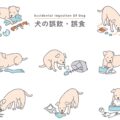 3
3
【獣医師執筆】犬が誤飲・誤食したかもしれない!チェックすべき症状と対処法。うんちで出るの?
-
 4
4
【獣医師執筆】犬に危険な植物・観葉植物は?室内や庭、お散歩時に要注意!
-
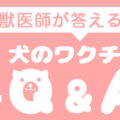 5
5
【獣医師が答える】犬のワクチンQ&A
-
 6
6
【獣医師執筆】犬の去勢手術はどうする?いつが適正?メリット・デメリットを知って考えよう
-
 7
7
【獣医師執筆】犬に蕎麦(そば)は与えてもOK。量や与え方、注意点などを詳しく解説
-
 8
8
犬に噛み癖をつけない、直すにはどうしたらいい?犬が飼い主を噛む原因と対処法
-
 9
9
【獣医師執筆】犬にネギは絶対あげちゃダメ。危険な量や症状、対処法を詳しく解説
-
 10
10
【獣医師執筆】犬の避妊手術はするべき?時期や費用、メリット、デメリットなどを詳しく解説





